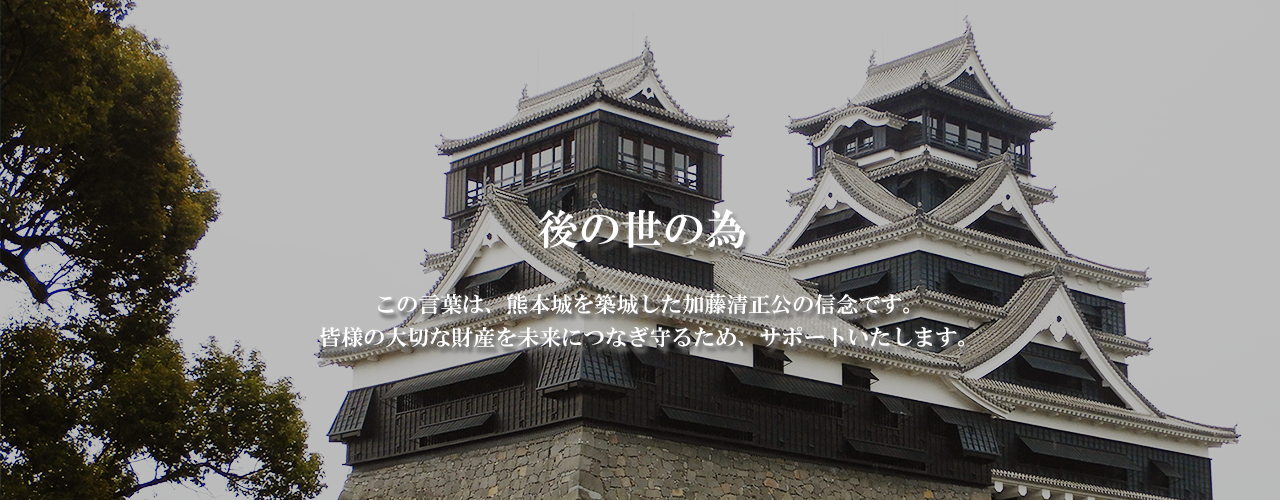
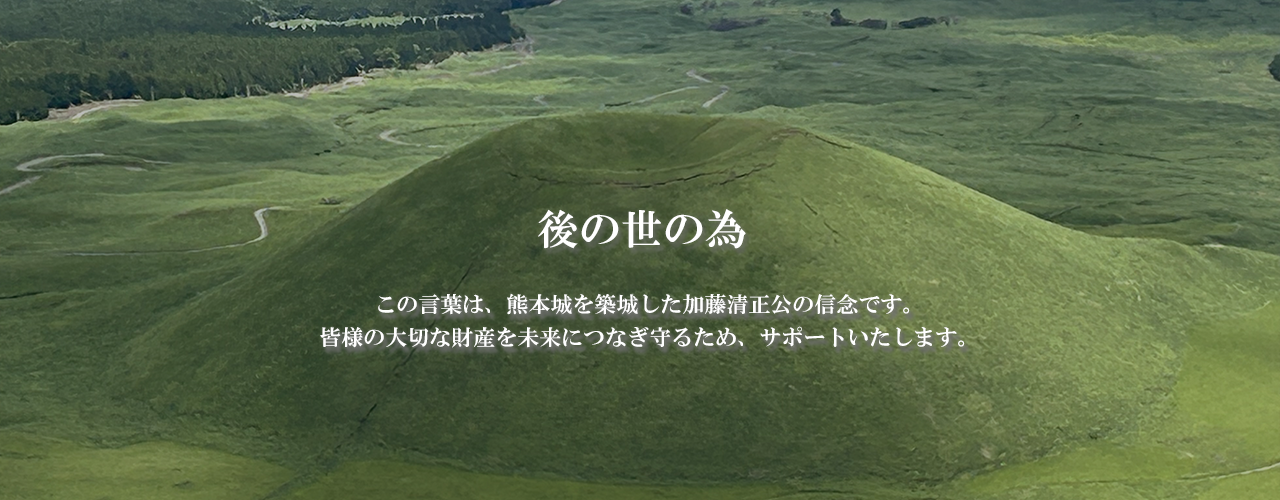
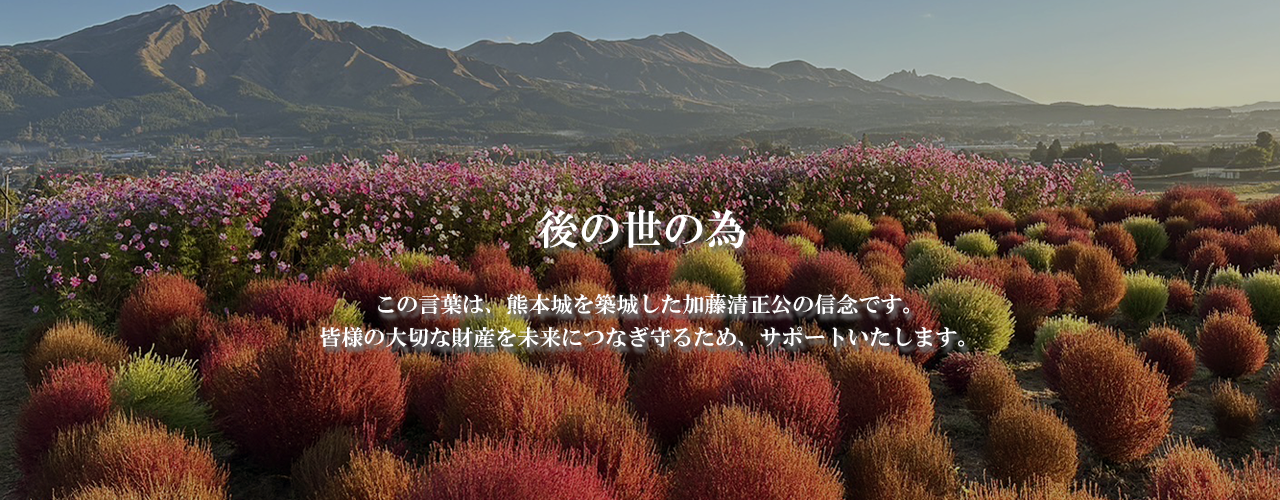
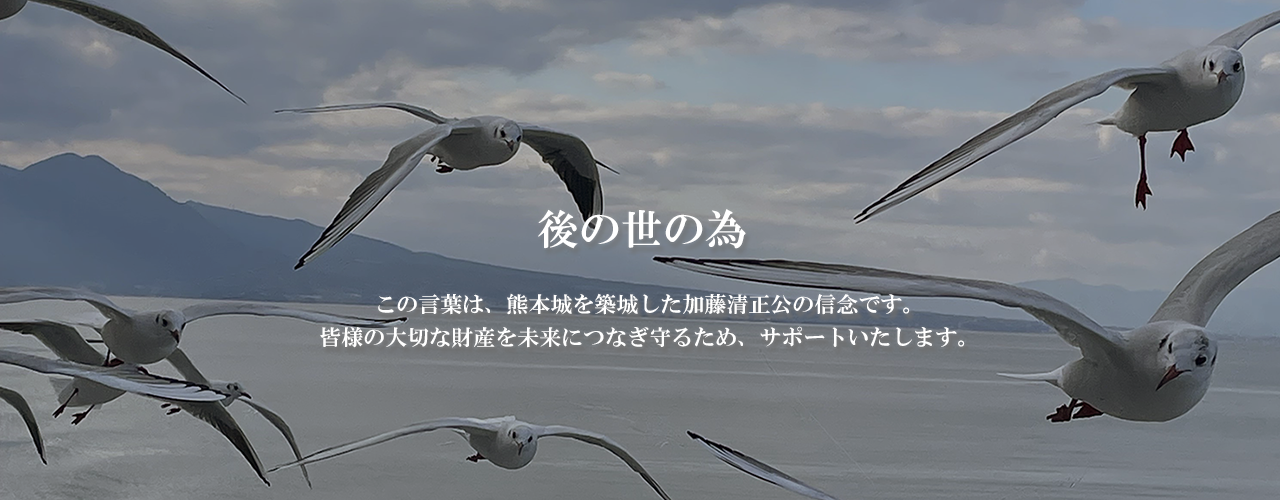

mv_0325
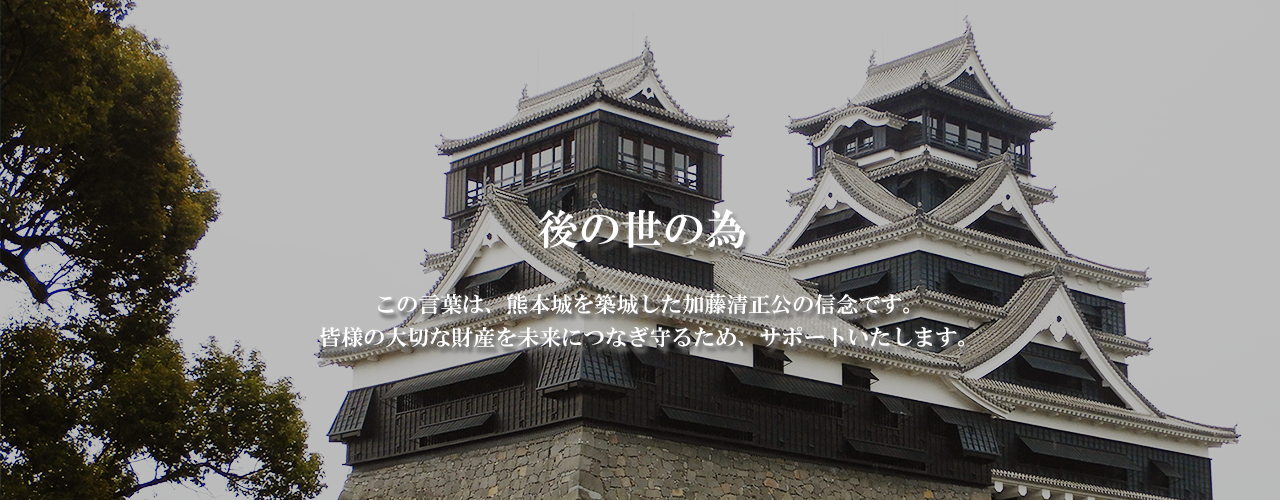
mv2
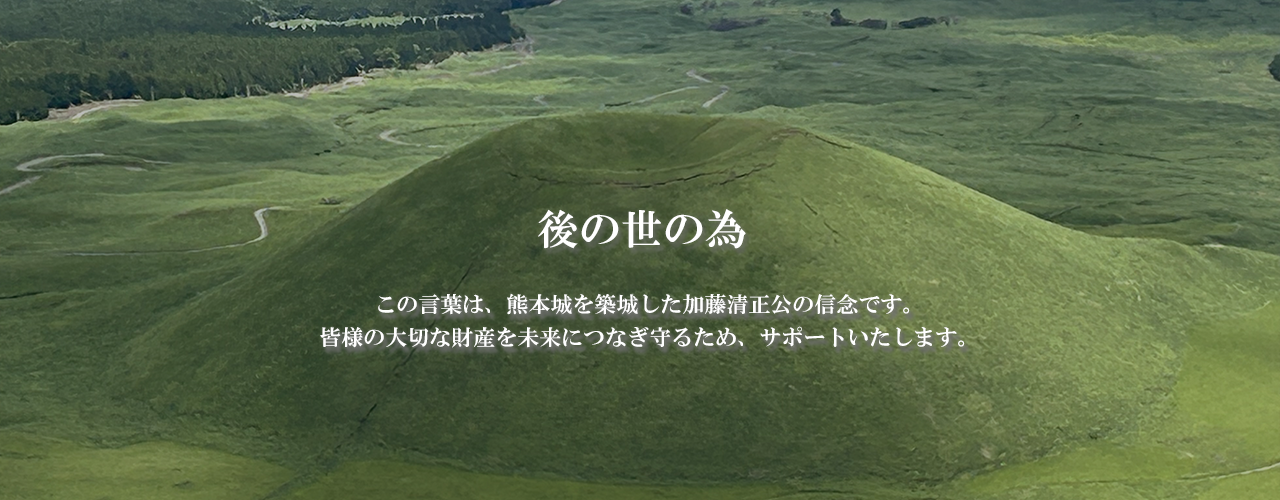
mv4
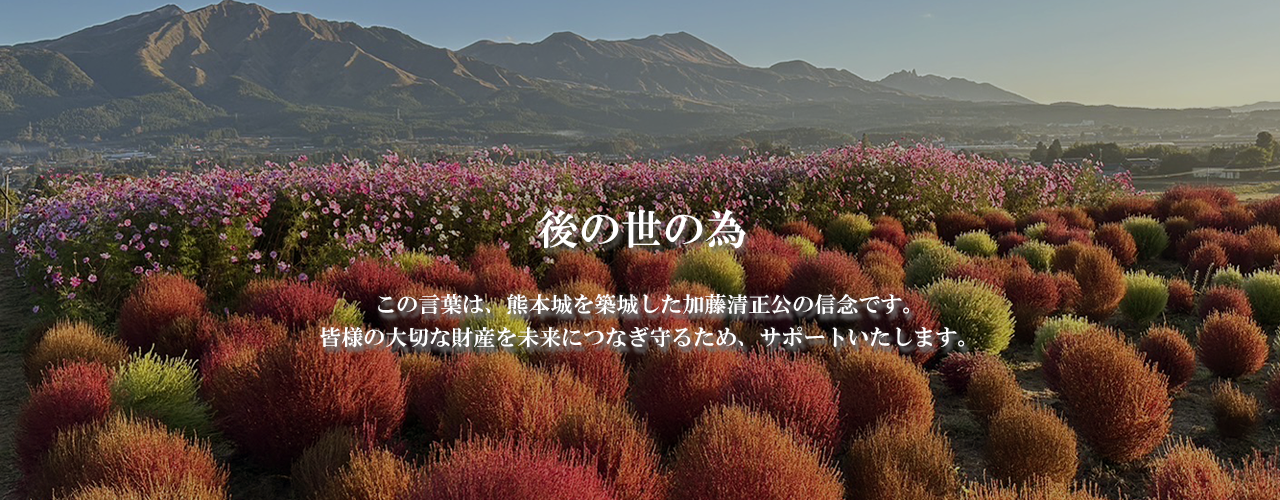
mv5
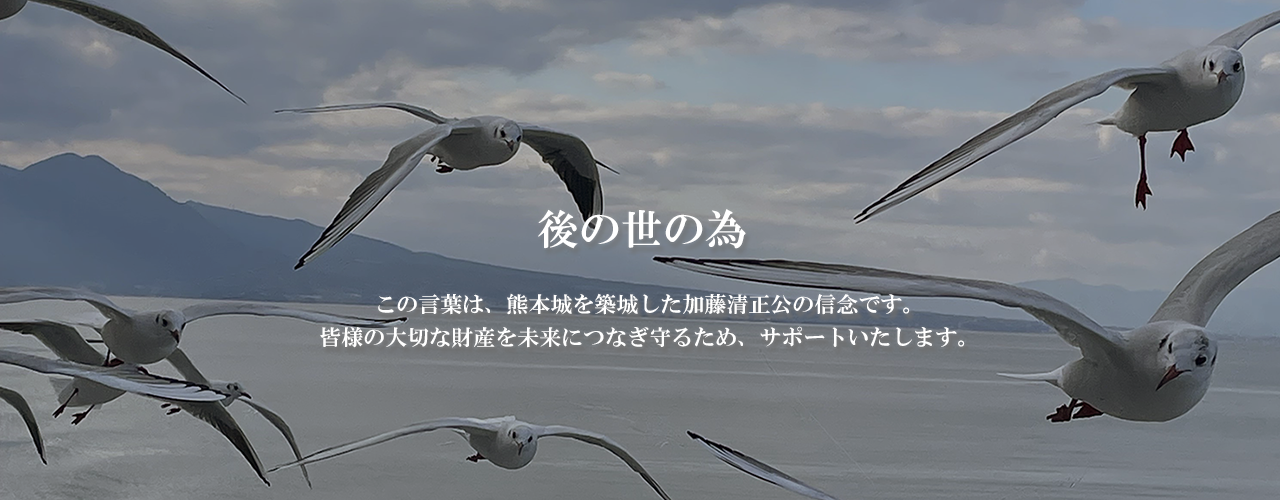
mv3

新築住宅が完成したら、1ヶ月以内に建物表題登記の申請が法律で義務付けられています。この登記により、建物の所在地番、家屋番号、種類(居宅・店舗・事務所等)、構造(木造・鉄骨造等)、屋根の種類、階数、床面積などが登記簿に記録されます。金融機関から住宅ローンを借りる際には、この登記が完了していることが条件となることがほとんどです。
中古住宅を購入した際、まれに建物が未登記の場合があります。特に古い建物や、増築を繰り返した建物に多く見られます。未登記のままでは、所有権を第三者に主張できず、売却や相続の際に大きな支障となります。購入後速やかに建物表題登記を申請し、その後所有権保存登記を行うことで、正式な所有者として登記されます。
建物表題登記の申請には、建築確認済証、検査済証、工事施工者の証明書、建物図面・各階平面図などが必要です。これらの書類が揃わない場合でも、代替書類で対応できることがありますので、まずはご相談ください。
リフォームで部屋を増築した、老朽化した部分を取り壊したなど、建物の床面積に変更があった場合は、変更後1ヶ月以内に登記申請が必要です。実際の建物と登記内容が異なると、固定資産税の課税に影響したり、売買時の重要事項説明に齟齬が生じたりする可能性があります。特に増築の場合、建築確認を取らずに行った部分は登記できない場合もありますので、事前の確認が重要です。
母屋とは別に車庫や物置を新築した場合、一定の要件を満たせば附属建物として登記できます。附属建物として登記することで、主たる建物と一体として扱われ、売買や相続の際に別々に処理する必要がなくなります。ただし、規模や用途によっては別個の建物として登記すべき場合もあります。
店舗だった建物を住宅に改装した、住宅の一部を事務所にしたなど、建物の用途が変わった場合も変更登記が必要です。用途の変更は固定資産税の評価にも影響しますので、実態に合わせた登記をすることが大切です。
建物を取り壊した場合、取壊しから1ヶ月以内に滅失登記を申請する必要があります。この登記を怠ると、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けることになります。解体業者から取壊し証明書を受け取り、速やかに手続きを進めましょう。建て替えの場合は、まず既存建物の滅失登記を行ってから、新築建物の表題登記を行います。
実際には存在しない建物が登記簿に残っている場合があります。火災で焼失した建物、自然災害で倒壊した建物、かなり前に取り壊したが登記を忘れていた建物などです。このような場合も滅失登記により、登記簿を現況に合わせることができます。長期間放置すると、相続時に問題が複雑化することがあります。
建物に抵当権などの担保権が設定されている場合は、権利者の承諾が必要になることがあります。また、共有建物の場合は共有者全員からの申請が原則となります。事前に登記簿を確認し、必要な手続きを整理することが大切です。
車庫や倉庫などの附属建物だけを売却したい場合、まず附属建物を主たる建物から分離する「建物分割登記」が必要です。これにより、附属建物が独立した建物として登記され、単独で売買できるようになります。ただし、建築基準法上の制限により分割できない場合もあります。
隣接する複数の建物を構造上一体化した場合、建物合体登記により一個の建物として登記できます。増築により既存建物と新築部分が一体となった場合も同様です。合体により管理が簡素化され、将来の取引もスムーズになります。
マンションのような区分所有建物に関する特殊な登記もあります。専有部分と共用部分の区別、敷地権の設定など、通常の建物とは異なる複雑な手続きが必要となります。