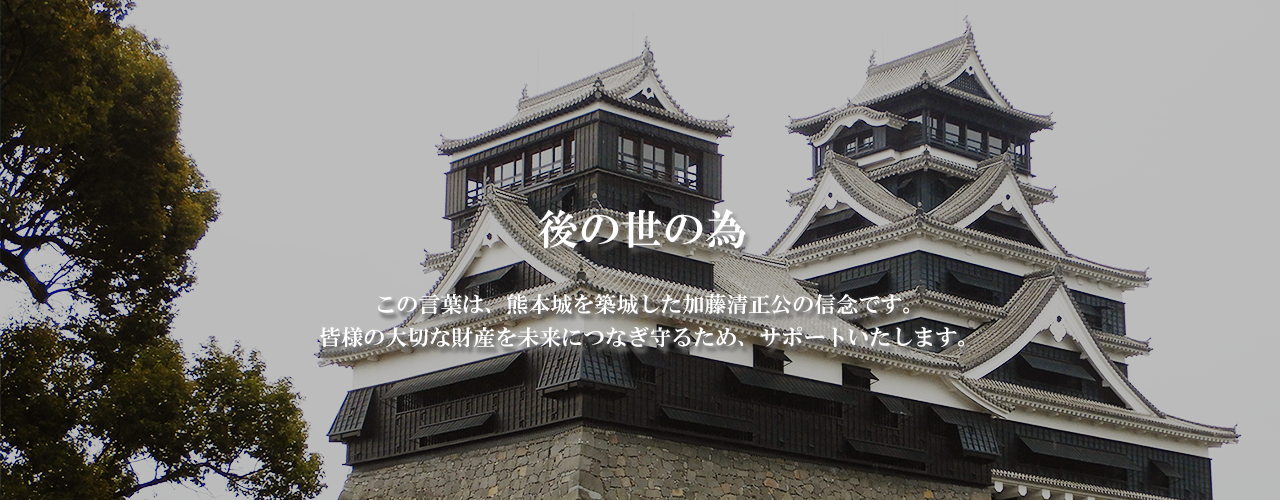
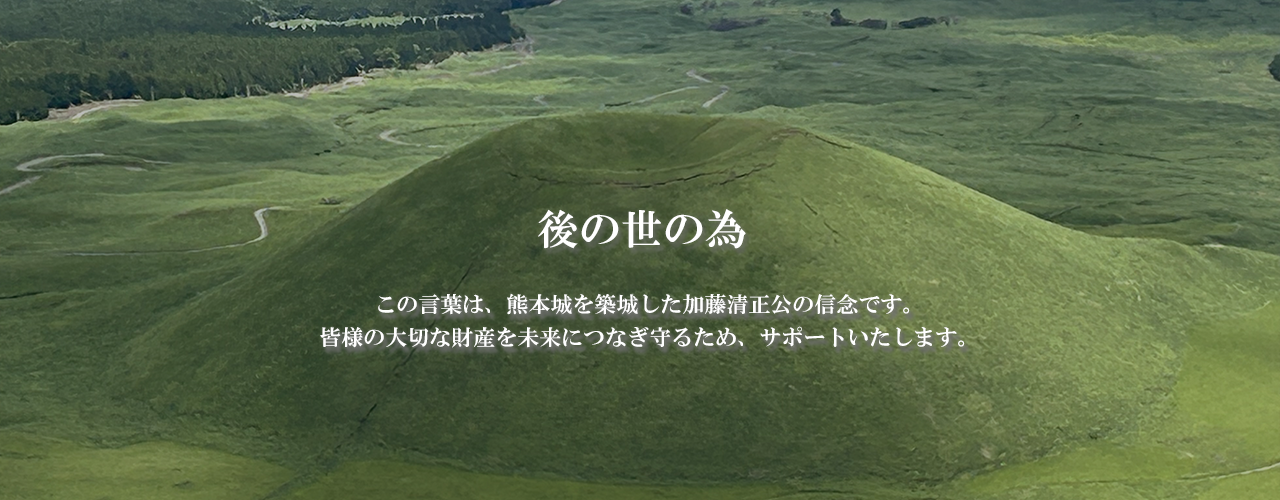
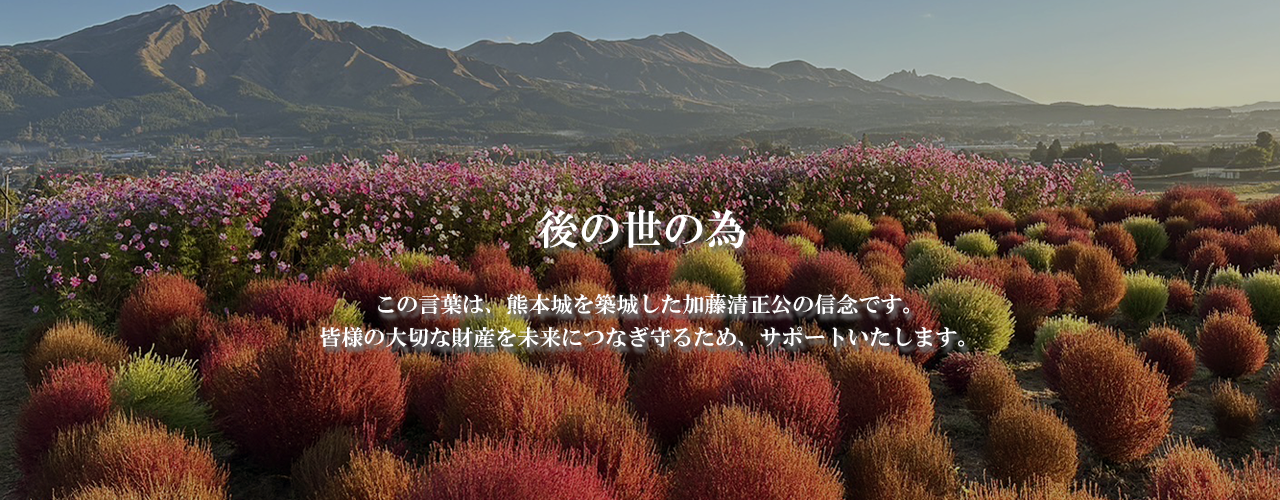
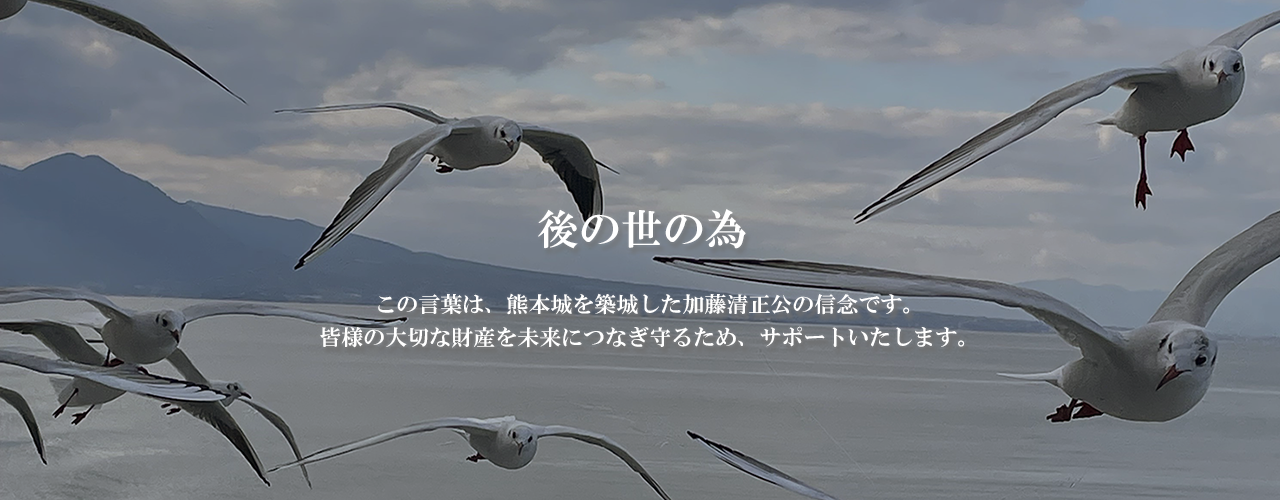

mv_0325
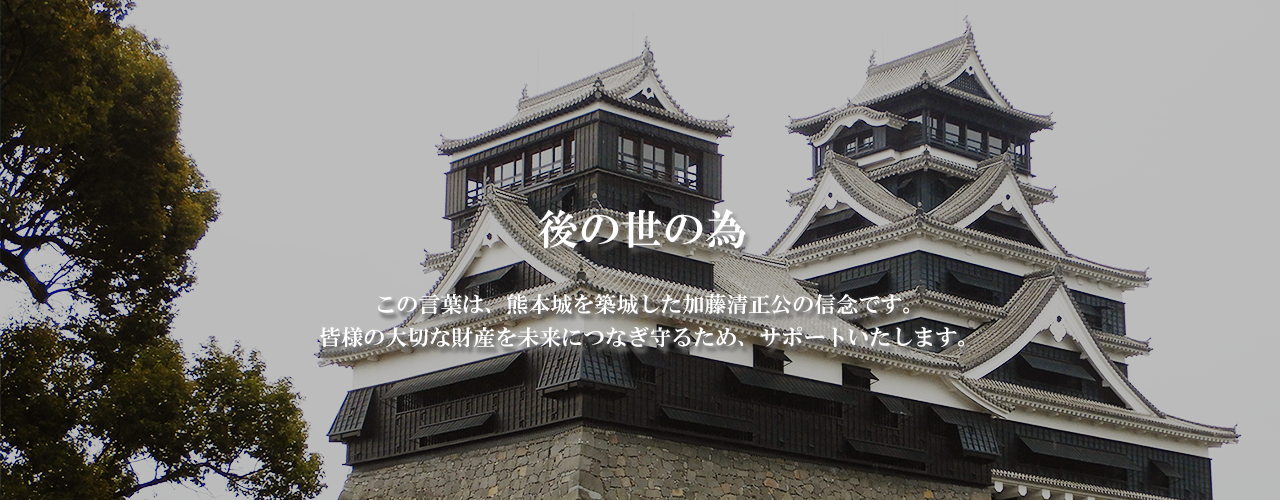
mv2
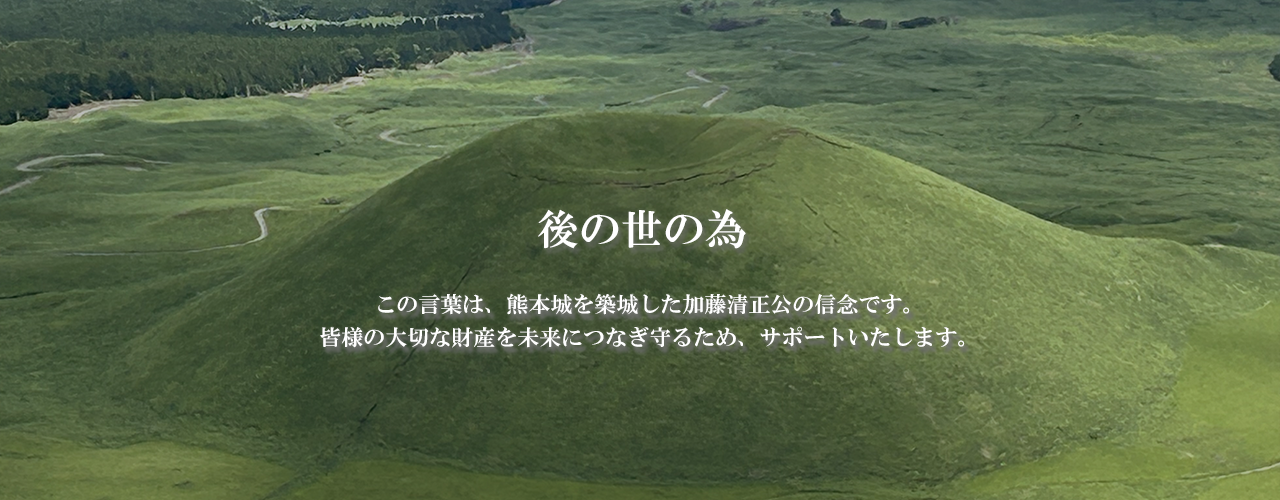
mv4
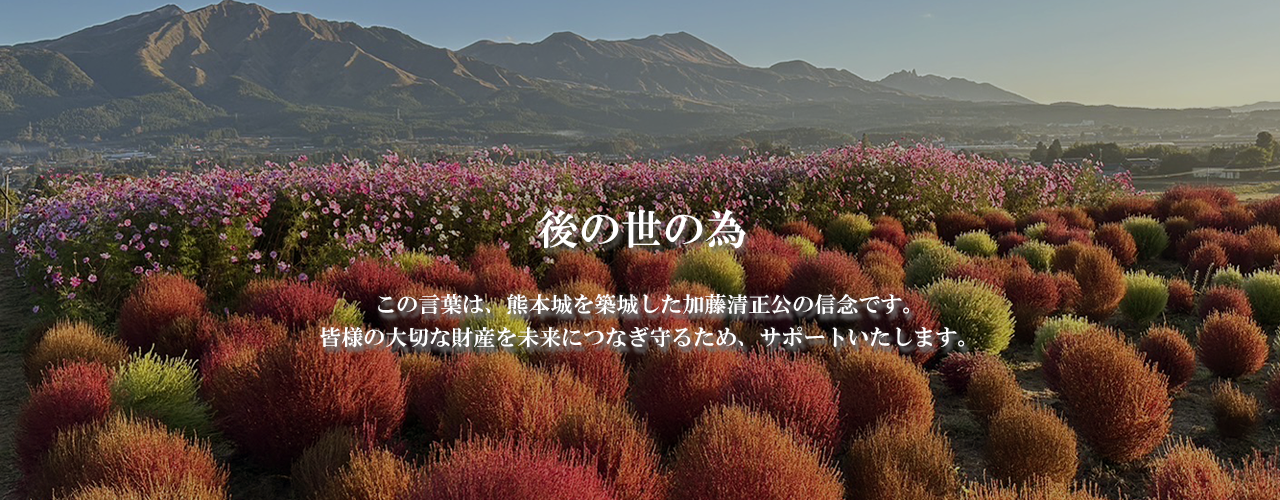
mv5
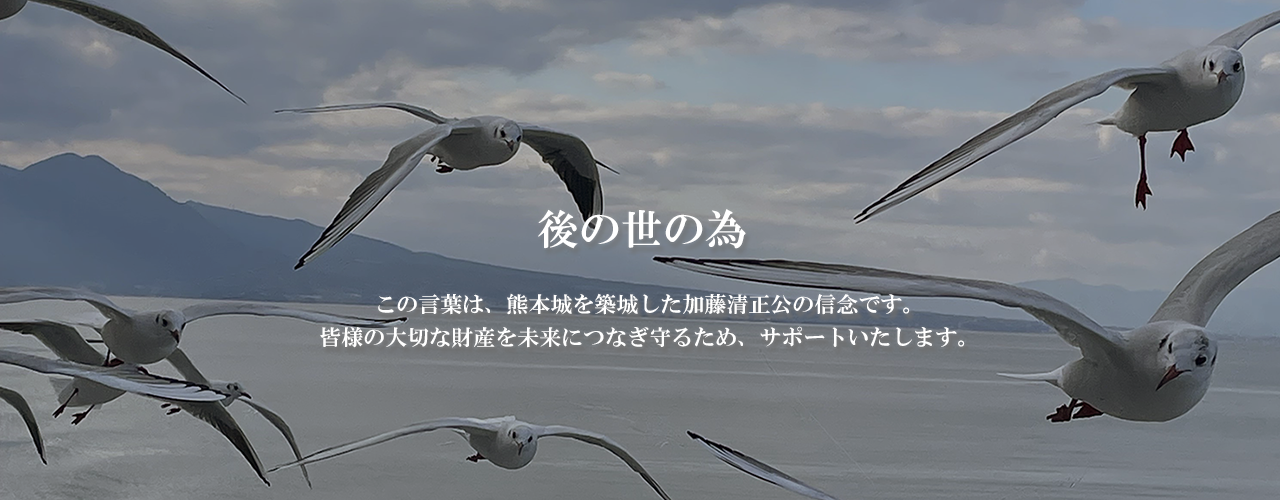
mv3

正確な測量は、土地の価値を明確にし、将来のトラブルを防ぐために欠かせません。最新の測量機器と技術により、精度の高い成果をご提供いたします。
「ブロック塀の中心が境界」「この木が目印」といった曖昧な認識は、将来の紛争の種となります。境界確定測量では、隣接土地所有者全員の立会いのもと、お互いが納得できる境界を確定します。過去の測量図、公図、航空写真などの資料を総合的に検討し、最も合理的な境界線を見出します。確定した境界には永続性のある境界標を設置し、復元可能な状態にします。
道路との境界(官民境界)の確定は、道路管理者(市町村、都道府県、国)との立会いが必要です。道路の幅員を確保するため、セットバックが必要な場合もあります。官民境界が確定することで、建築確認申請や開発許可申請がスムーズに進みます。また、道路の払い下げを受ける際の前提条件にもなります。
まず、法務局や市役所で公図、登記簿、道路台帳などの資料を収集します。次に現地の事前調査を行い、既存の境界標や目印となる構造物を確認します。その後、仮測量を実施し、隣接土地所有者へ立会いを依頼します。立会い当日は、すべての関係者が現地で境界を確認し、合意が得られれば境界確認書を作成します。最後に、境界標を設置し、確定測量図を作成します。
土地の概算面積を知りたい、建築計画の参考にしたい、といった場合は現況測量が適しています。現地にある塀やフェンスなどを基準に測量するため、境界確定測量と比べて短期間・低コストで実施できます。ただし、隣地との立会いを行わないため、境界を確定するものではないことにご注意ください。
敷地内の建物の位置、塀までの距離、道路からの後退距離などを測量します。建築基準法の制限(建ぺい率、容積率、斜線制限など)を確認する際の基礎資料となります。増築やリフォームを計画する際には、まず現況を正確に把握することが大切です。
不動産の売買において、買主が購入判断をする際の参考資料として活用されます。また、相続財産の概算評価、建物の建築計画、外構工事の見積もりなど、様々な場面で利用されます。将来的に境界確定測量を行う予定がある場合は、その準備段階としても有効です。
工事や災害で境界標が亡失した場合、過去の測量成果を基に境界を復元します。以前に境界確定測量を行っていれば、その座標データから正確な位置に境界標を再設置できます。境界標がないままにしておくと、お隣との認識の違いから紛争に発展する可能性があります。
境界標には、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭などがあります。それぞれ耐久性や視認性が異なりますので、設置場所に応じて適切なものを選択します。定期的に境界標の状態を確認し、破損や傾きがあれば早めに修復することが大切です。
過去の測量成果がない場合は、関係者の記憶や現地の状況証拠から境界を推定することになりますが、この場合は改めて境界確定測量を行うことをお勧めします。また、復元の際も隣接土地所有者に立会いを求め、認識の相違がないか確認することが重要です。
傾斜地や高低差のある土地では、正確な高低差を把握することが重要です。建築計画では、道路との高低差、隣地との高低差により、擁壁の必要性や建物の配置が決まります。また、排水計画や外構計画にも欠かせない情報です。水準測量により、ミリメートル単位の精度で高さを測定します。
建築基準法の日影規制や斜線制限を検討する際、真北の方向が必要になります。磁北と真北は地域により異なるため、正確な真北方向を測量により求めます。GPS測量や太陽観測により、高精度な真北方向を決定し、建築設計に必要な資料を提供します。
道路の新設や拡幅に伴う測量、大規模な開発に伴う測量など、特殊な測量にも対応いたします。これらの測量は、公共事業や民間の開発事業において必要不可欠なものです。計画段階から完成まで、一貫したサポートを提供いたします。