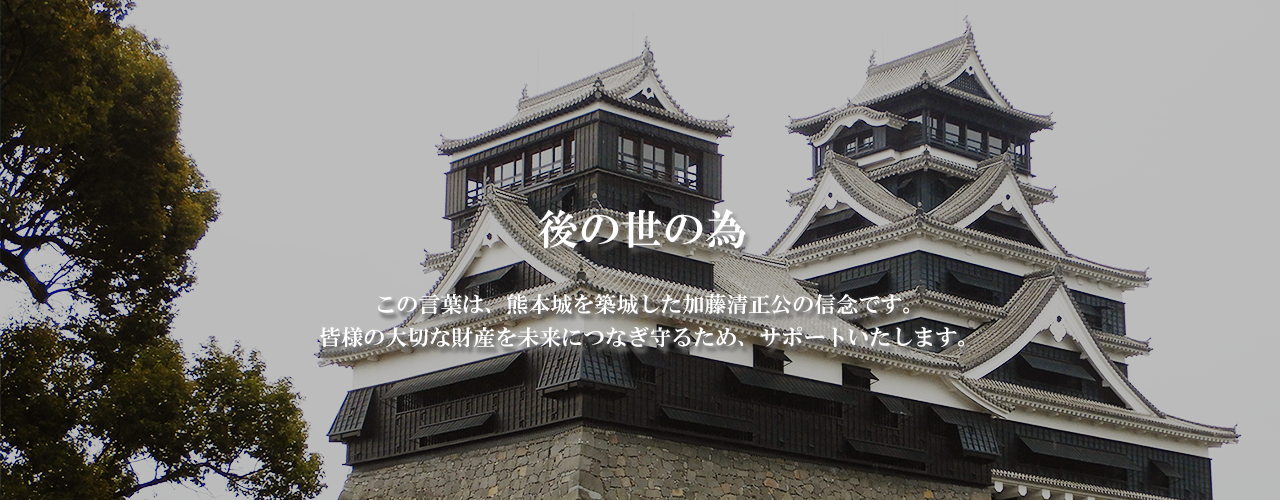
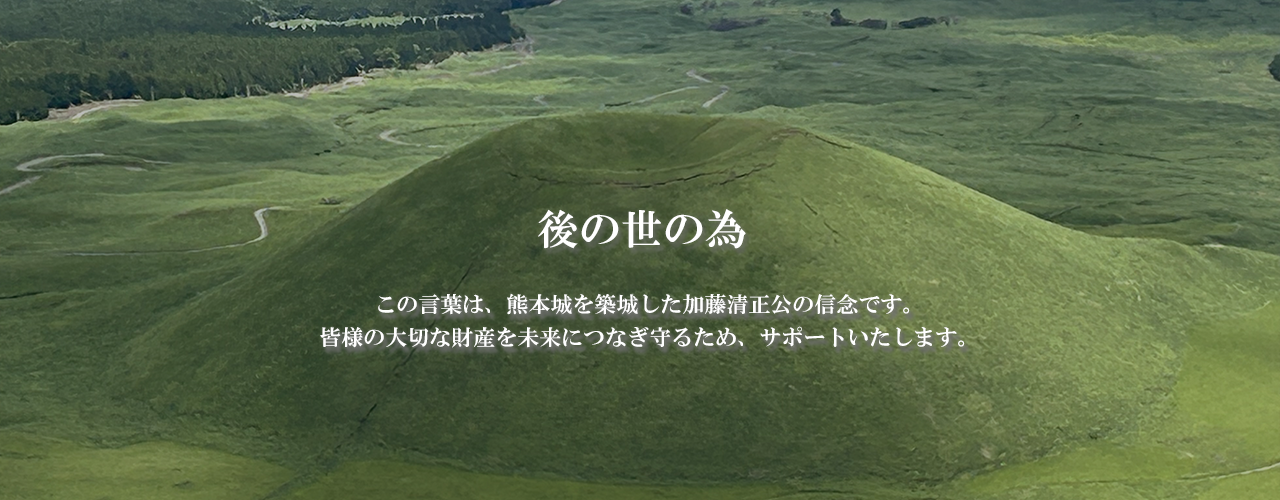
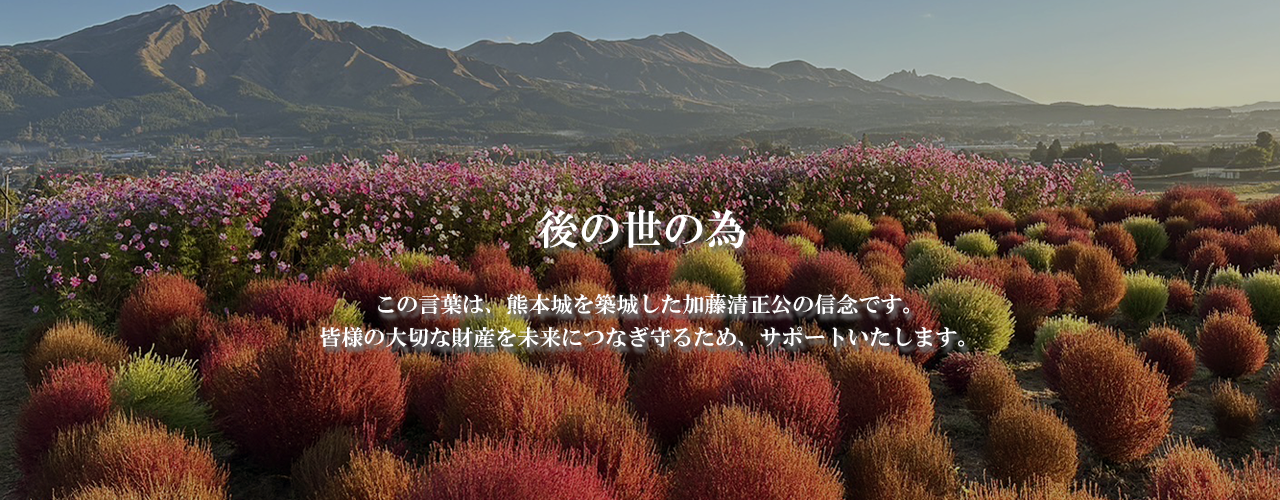
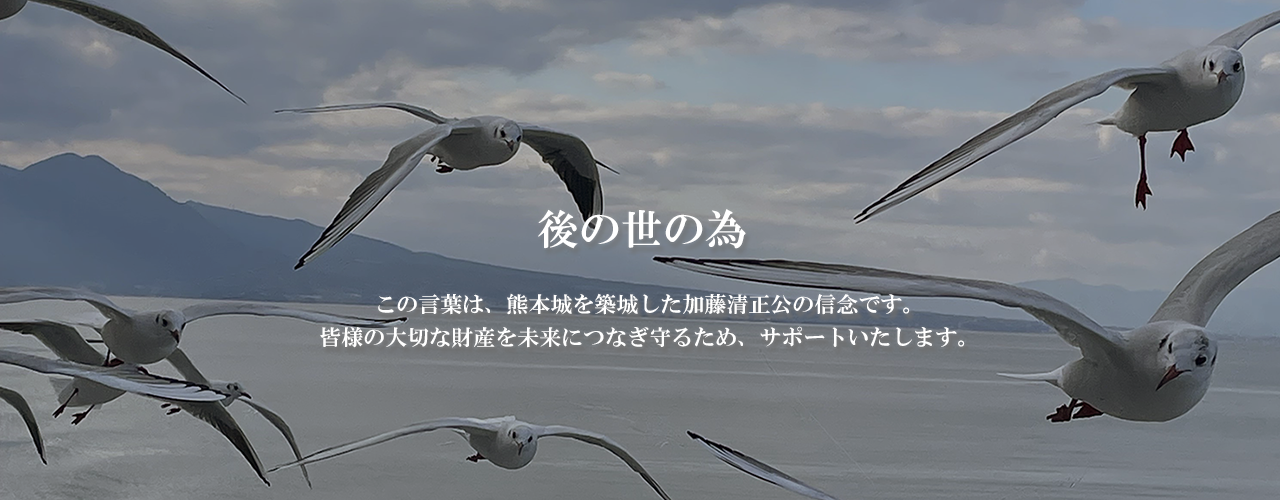

mv_0325
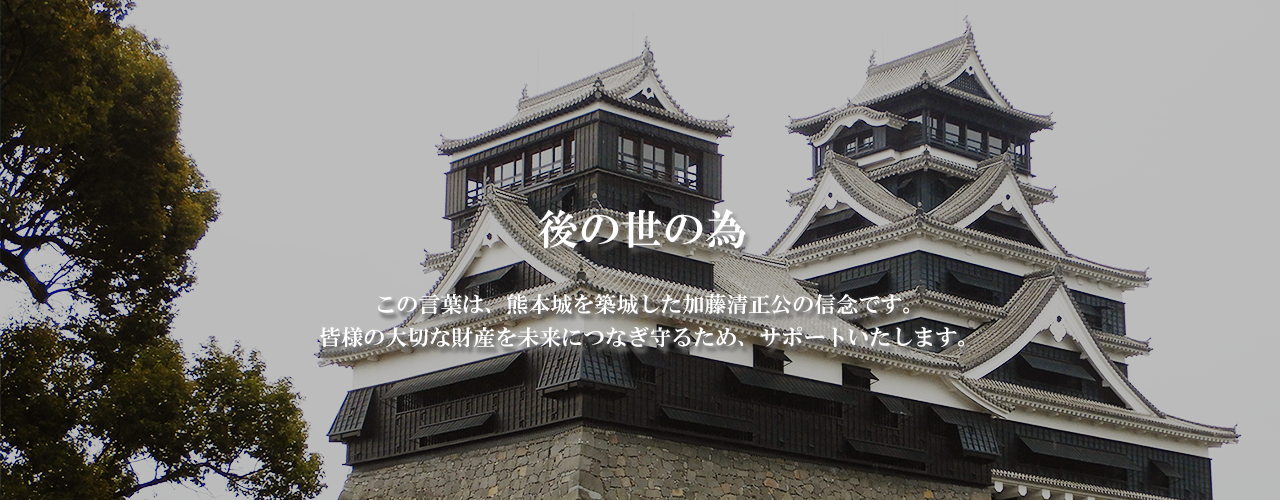
mv2
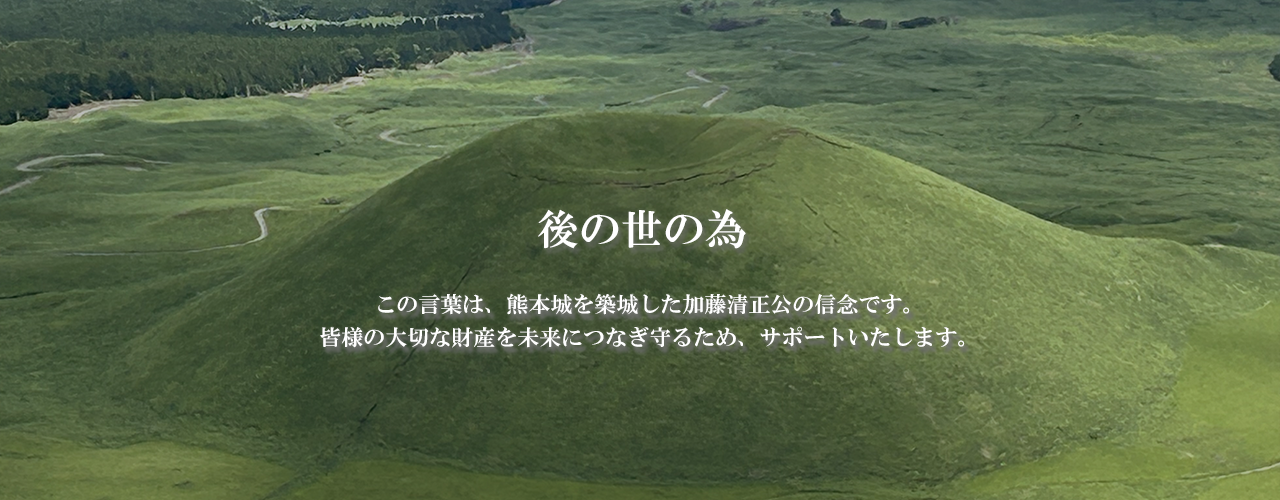
mv4
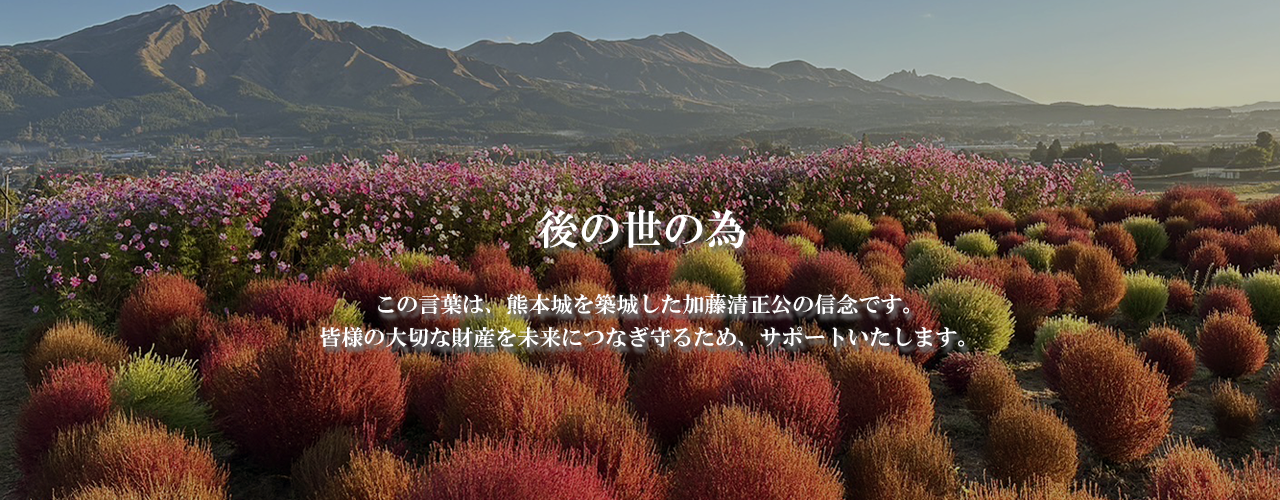
mv5
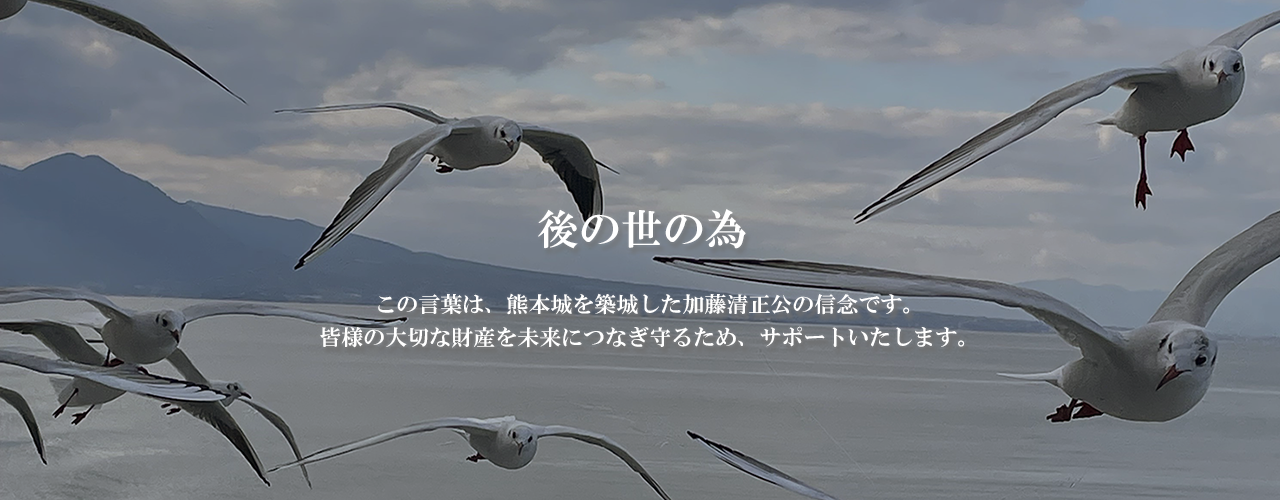
mv3

土地の境界に関する紛争は、当事者間では解決が困難な場合があります。そのような時は、公的な制度や専門家による調停を活用することで、円満な解決を図ることができます。
筆界(土地の境界)について隣接土地所有者との間で認識が異なる場合、法務局の筆界特定登記官が、専門的な調査を行い、もともとの筆界を特定する制度です。平成18年に創設されたこの制度は、裁判によらずに境界問題を解決できる画期的な制度として注目されています。
申請を受けた筆界特定登記官は、筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士等)を任命し、現地調査や測量、関係者からの意見聴取を行います。過去の地図、航空写真、登記記録などあらゆる資料を検討し、最も合理的と考えられる筆界を特定します。特定までの期間は概ね6ヶ月から1年程度です。
筆界特定により、登記官が筆界を明らかにしますが、これは行政処分ではなく、当事者の権利関係を確定するものではありません。しかし、公的機関による専門的な判断として、その後の解決に向けた有力な資料となります。特定結果に納得できない場合は、別途裁判で争うことも可能です。
土地家屋調査士会が運営するADR(Alternative Dispute Resolution)センターでは、土地の境界に関する紛争を、話し合いにより解決することを目指します。調停人として土地家屋調査士と弁護士が協働し、専門的知識と法的観点から、当事者双方が納得できる解決策を探ります。
裁判と比較して、手続きが簡易で費用も抑えられます。また、非公開で行われるため、プライバシーが守られます。何より、話し合いによる解決のため、隣人関係を維持しながら問題を解決できる可能性があります。調停の結果、合意に至れば、その内容を和解契約書にまとめ、将来の紛争防止に役立てることができます。
境界の位置についての争い、境界標の設置についての争い、越境物(塀、建物の一部、樹木等)の処理についての争い、境界確認書への署名を拒否されている場合など、土地の境界に関するあらゆる紛争が対象となります。まずは相談から始めることができますので、お気軽にご利用ください。