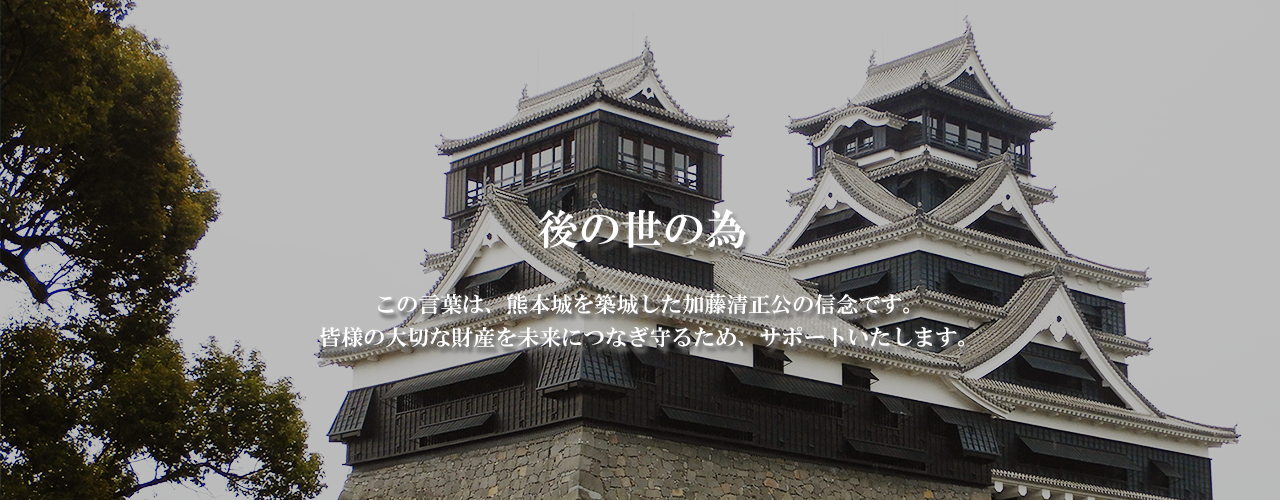
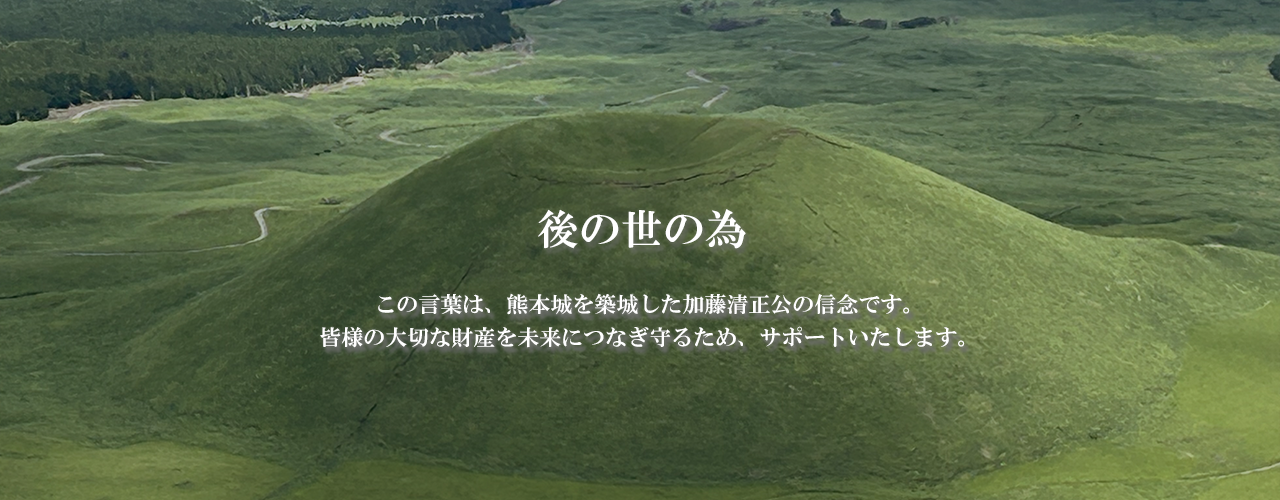
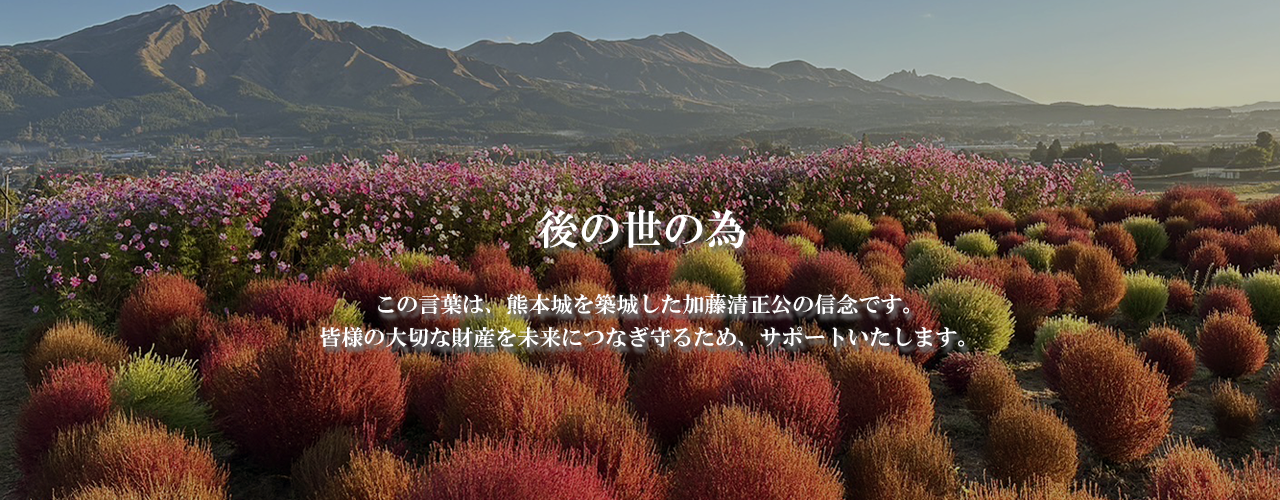
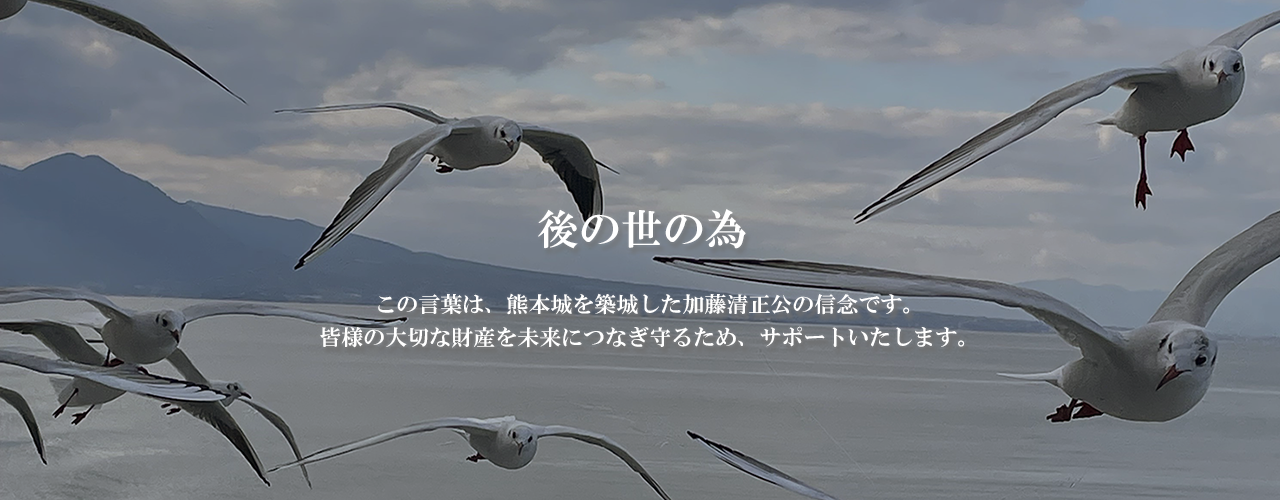

mv_0325
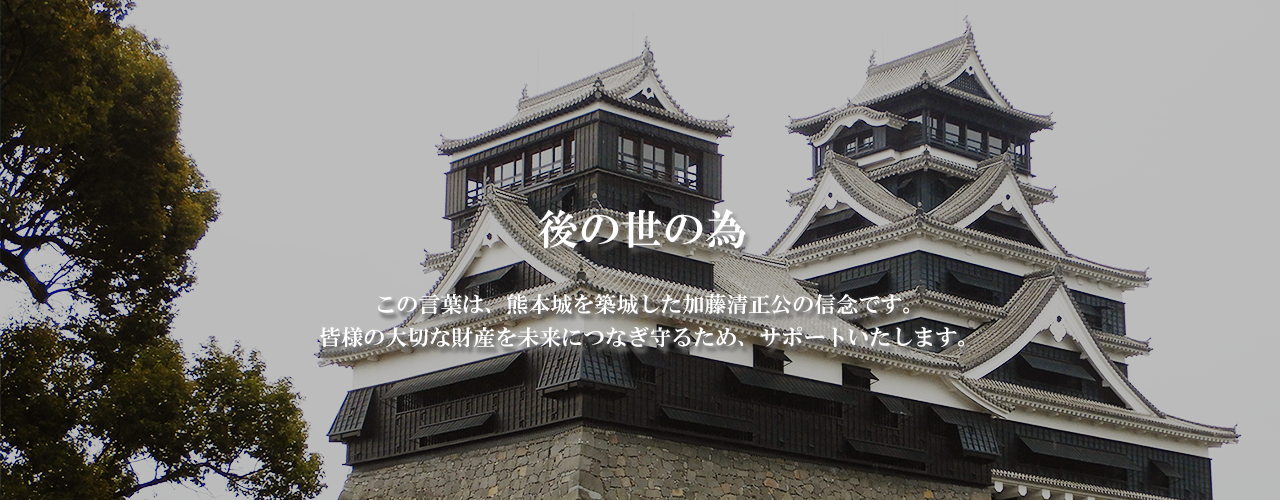
mv2
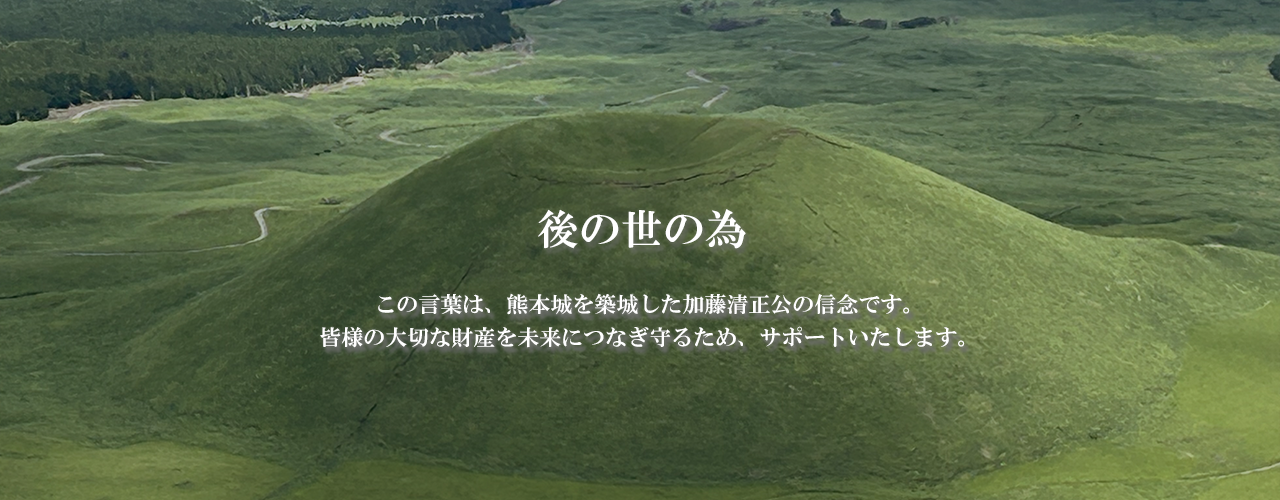
mv4
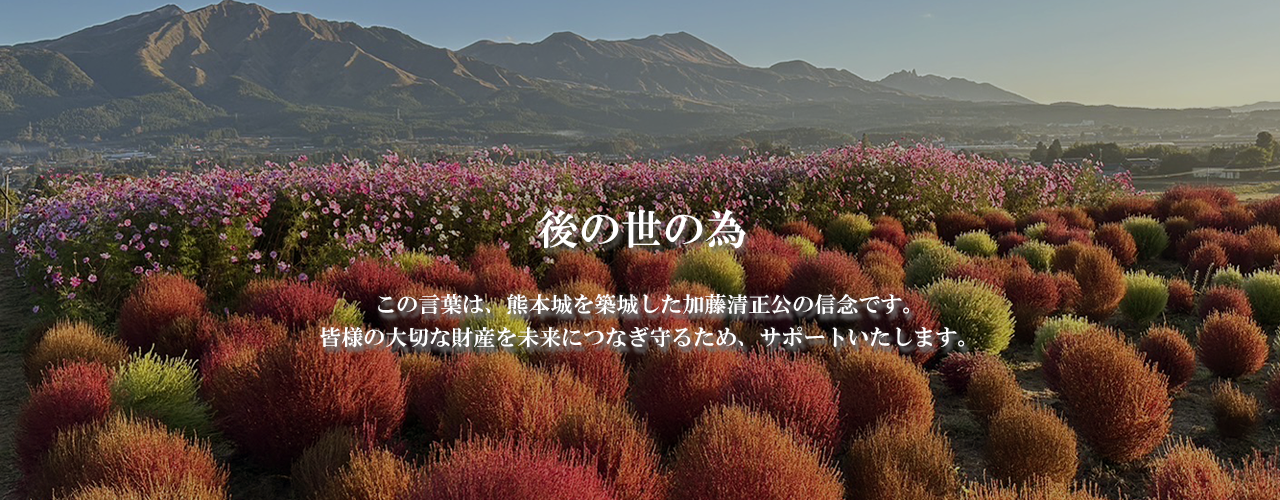
mv5
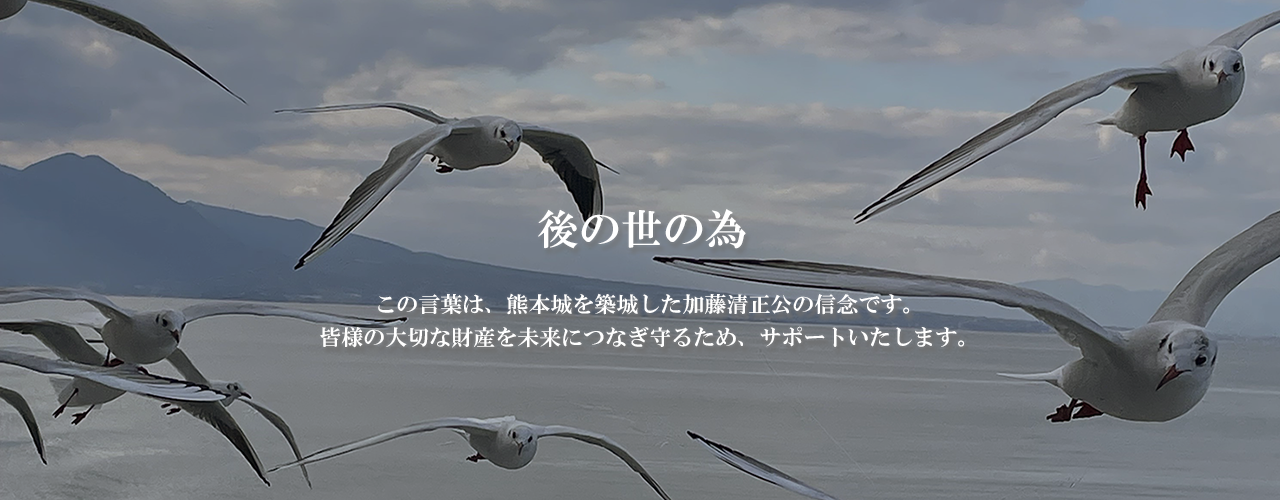
mv3

土地の表示に関する登記は、土地の物理的な状況を明確にし、取引の安全を図るための重要な制度です。正確な登記により、境界紛争の防止や適正な課税にもつながります。
公有水面の埋立てや干拓により新たに土地が造成された場合、土地表題登記が必要です。この登記により、初めて土地として法的に認められ、地番が付されます。埋立地の場合、竣工認可から1ヶ月以内に登記申請を行う必要があります。手続きには埋立免許書、竣工認可書、測量図面などの専門的な書類が必要となります。
国や地方公共団体から土地の払い下げを受けた場合も、土地表題登記が必要になることがあります。特に、道路や水路だった土地を払い下げを受けた場合、まず用途廃止の手続きを経てから表題登記を行います。これにより、私有地として正式に登記され、所有権の登記が可能になります。
昔からある里道(赤道)や水路(青道)が機能を失っている場合、隣接土地所有者は払い下げを受けることができます。この手続きは複雑で、関係者全員の同意や代替施設の確保など、様々な条件をクリアする必要があります。
土地の一部を売却する場合、まず土地を分筆して別々の地番を付ける必要があります。分筆により、売却する部分と残す部分がそれぞれ独立した土地となり、個別に取引できるようになります。分筆の際は、両方の土地が建築基準法上の接道義務を満たすよう注意が必要です。分筆後は、それぞれの土地に新しい地番が付され、公図も修正されます。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議により土地を物理的に分けることがあります。各相続人が独立して土地を利用・処分できるよう、分筆登記を行います。ただし、分筆により土地の利用価値が著しく下がる場合は、共有のままにするか、代償分割を検討することも大切です。
分筆登記には、事前の境界確定測量が必須です。隣接土地所有者全員の立会いのもと境界を確認し、境界確認書を作成します。その後、地積測量図を作成し、登記申請を行います。費用は土地の規模や隣接地の数により異なりますが、測量費用と登記費用を合わせて検討する必要があります。
隣接する複数の土地を所有している場合、合筆登記により一つの土地にまとめることができます。これにより、管理が簡素化され、固定資産税の納付も一本化されます。また、建築計画を立てる際も、一つの敷地として扱えるため手続きがスムーズになります。ただし、登記簿上の地目が異なる土地は合筆できません。
合筆できる土地には条件があります。隣接していること、同一の地目であること、所有者が同じであること、抵当権などの所有権以外の権利の登記がないこと(または同一の権利であること)などです。これらの要件を満たさない場合は、事前に地目変更や抵当権抹消などの手続きが必要となります。
メリットとしては、管理の簡素化、登記費用の節約、売買手続きの簡略化などがあります。一方、デメリットとしては、将来分筆したくなった場合に改めて測量が必要になること、部分的な売却が難しくなることなどが挙げられます。将来の土地利用計画を考慮して判断することが大切です。
田や畑だった土地に建物を建てた場合、土地の地目を「宅地」に変更する必要があります。農地から宅地への変更は、事前に農地転用許可を受けている必要があります。地目変更により、固定資産税の評価も変わりますので、税負担の変化も考慮しておくことが重要です。変更から1ヶ月以内の登記申請が義務付けられています。
駐車場として利用していた土地を宅地にした、宅地だった土地を資材置場にしたなど、土地の主たる利用目的が変わった場合は地目変更登記が必要です。現況主義により、登記官が実地調査を行い、実際の利用状況に基づいて地目を認定します。
地目には、宅地、田、畑、山林、雑種地など23種類があります。それぞれの地目には明確な判断基準があり、土地の現況と利用目的により決定されます。複数の用途で使用している場合は、主たる用途により地目が決まります。地目により税負担が大きく変わることもあるため、適切な地目での登記が重要です。
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が異なることはよくあります。特に古い登記の土地では、測量技術の違いから大きな差が生じていることがあります。売買契約を実測面積で行う場合や、正確な財産評価が必要な場合は、地積更正登記により正しい面積に修正します。
地積更正登記を行うには、すべての境界が確定している必要があります。隣接土地所有者、道路管理者などの立会いのもと、境界を確定し、境界標を設置します。この作業には時間がかかることもありますが、将来の紛争防止のためにも重要な手続きです。
正確な面積が登記されることで、適正な固定資産税評価につながります。また、実測売買の際の説明責任を果たすことができ、買主からの信頼も得られます。相続税の申告においても、正確な面積での評価が可能になります。
相続や売買により所有者が変わっているのに、表題部の所有者欄が古いままになっている場合があります。また、住所や氏名に誤りがある場合もあります。これらは更正登記により正しい内容に修正できます。特に相続が数代にわたって行われている場合は、遡って相続関係を証明する必要があり、専門的な知識が求められます。
法務局に備え付けられている地図(公図)に誤りがある場合、地図訂正の申出を行うことができます。境界の位置や土地の形状が実際と異なる場合、測量成果に基づいて訂正を求めます。これにより、登記の公示機能が適切に果たされるようになります。
境界確定の際に作成する筆界確認書は、将来の紛争防止に重要な書類です。隣接土地所有者と境界について合意した内容を書面化し、双方が署名押印します。この書類は登記申請の添付書類としても使用されます。